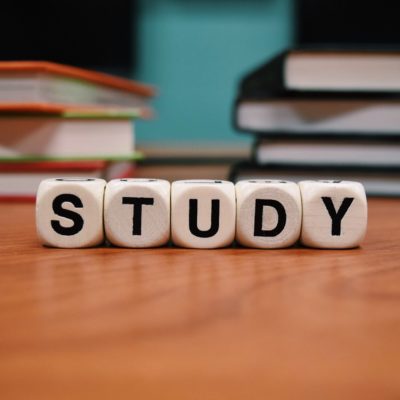子どもを注目させる方法が知りたい方へ
子どもを注目させるとき、注意してしまいます。楽しくこちらに惹きつける方法はありませんか?
こういったお悩みにお答えします。
✔️本記事の内容
・子どもを注意せずに注目させる方法
①だるまさんが〇〇
②王様が言いました
③命令!〇〇
④もぐもぐゲーム
・子どもに合わせてカスタマイズする
✔️補足
この記事を書いている私は、4年間の教員経験があります。
子どもの集中力は短いもの。ずっと先生の方を向いていられる子ばかりではありません。
そのような時に、どのように注目させたら良いか。今回は小学校低学年に効果的な方法をご紹介します。
スポンサードサーチ
子どもを注意せずに注目させる方法
注意はお互い辛い
「静かに」「こっち見て」などの注意でこちらを向かせるのは、大人側も辛いし、子どもも辛いですよね。
だんだん大人も子どももイライラしてきてしまったり。
子どもが自然にこちらに向いてくれたら、お互いにハッピーですよね。
無理やりではなく惹きつける
「面白そう」「楽しいことが起きそう」という気持ちにさせて、注目させる方法が一番です。
特に小さい子どもは正直なので、楽しそうなことに惹きつけられ、つまらなそうと思うことからは即座に引いていきます。とっても分かりやすいです。
また、同じことをやっても飽きやすいので、飽きさせない工夫が大切。
簡単なゲームを2、3分でやる
子どもの集中力が切れてきたな、と思ったら、簡単なゲームをするのがおすすめです。
気分転換にもなるし、子どもが惹きつけられるし、数分かけても無駄な時間にはならないです。
次からは、実際に教員時代にやっていた、子どもをすっと注目させる簡単なゲームを詳しく説明していきます。
元々はソーシャルスキルトレーニングなどで使われているものが多いですが、一瞬でできるものなので、子どもを惹きつけたい時に軽くやると効果的です。
①だるまさんが〇〇
だるまさんが転んだ!ののりで行うので、子どもたちが親しみやすいゲーム。
だるまさんが〇〇の、〇〇の部分を子どもが真似するというゲームです。
教師:「だるまさんが寝た!」
子ども:寝たふりをする
教師:「だるまさんが笑った!」
子ども:笑う
教師:「だるまさんが泣いた!」
子ども:泣き真似をする
こんな感じです。
ネタはなんでもよくて、あくびした、立った、黙った、座った、頭をかいた、耳を触ったなどなど。アレンジ次第で無限大です。
「笑った」など、あまりうるさくなりすぎるのが嫌な場合は、静かに真似できるものをチョイスするのが良いです。
スポンサードサーチ
②王様が言いました
だるまさんと似ています。
教師:「王様が言いました。あくびをする!」
子ども:あくびをする
教師:「王様が言いました。ひそひそ話をする」
子ども:ひそひそ話をする
教師:「王様が言いました。先生を褒める!」
子ども:(きっとたくさん褒めてくれるはず。笑)
こんな感じで、だるまさんと基本一緒ですが、掛け声が違うだけ。
でも子どもにとっては掛け声の違いは大きな問題のようで、全く違うゲームと言う認識の子もいます。
③命令!〇〇
だるまさんや、王様と同じ。
教師:「命令!手をお膝にする」
子ども:手を膝にする
教師:「命令!お隣さんを褒める」
子ども:「隣の子を褒める」
教師:「命令!右手をあげる」
子ども:右手をあげる
このようにやります。
子どもたちの好き嫌いによって、だるまさん、王様、命令を使い分けるのが良いです。
あとは、同じゲームだとすぐ飽きてしまうので、3つをうまく使い分けるのがおすすめです。
スポンサードサーチ
④もぐもぐゲーム
タンタンタンのリズムで行います。
教師:「りんご」はい!
子ども:「もぐもぐもぐ」
教師:「お水」はい!
子ども:「ごくごくごく」
教師:「みかん」はい!
子ども:「もぐもぐもぐ」
ルールを説明すると、
食べ物だったら→もぐもぐもぐ
飲み物だったら→ごくごくごく
このゲームを始めた経緯は、
1年生の担任だった時に、子どもが楽しめて、隙間時間にできるゲームないかなーと考えていた時に、思いついたゲームです。
やってみると、語彙も増やせて、リズム感も鍛えられて、反射神経も鍛えられるという画期的なゲームでした。
そのうち子どもたちが勝手に発展させて、「うどん」「ずるずるずる」など休み時間にやっていました。「ランドセル」「らんらんらん」とかも言ってました。ルールは謎です(笑)
子どもに合わせてカスタマイズする
色々なゲームがあるので、時と場合に応じて回数や役割を変えるのがおすすめです。
時間がある時は、教師役を子どもにやらせてもいいです。
子どもに教師役をやらせる時は、事前に約束をすると良いです。
・痛いことはしない
・人が嫌がることはしない
この2点を約束しておくとスムーズだし、子どもも安心してできます。
今回は以上となります。子どもも教育者も気持ちよく過ごせるように一工夫。参考になったら幸いです(^^)